- 現在位置:
-
- みっぷる広場
- > 家庭教育応援Web講座
- > 家庭教育応援Web講座吉田先生
吉田 賢一先生
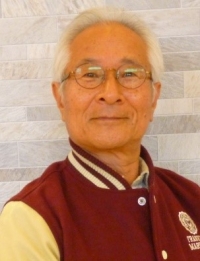
先日、公民館のホールを会場にして親子(幼児、園児)と祖母(の年代の集まり)を対象に遊びをともにする機会を得ました。
いくつかの遊び道具をホールに広げて、気に入った道具で遊ぶ子ども達。親が遊びを手助けしたり、祖母等は時々転がってくるボールを返す時に「上手、上手」と褒めたりして、和やかな雰囲気の中で時間が進んでいきました。
用意した遊び道具の中に「ボーリングセット」がありました。プラスチックのピンが10本。それを倒すためのソフトボール大のプラスチックの球。ボールがピンに確実に当たるようにと、自作した木製のガードも用意して、取り合いになるだろうと予想したこの遊びが大誤算。
子ども達は何度も挑戦するのですが、5,6本は倒れてもなかなかストライクにはなりません。ピンの並べ方や投げる距離を変えても、結果はあまり変わりません。周りからは、「もう少し」とか「おしい」などの声がかかりますが、子ども達のやる気は萎えるばかり。とうとう誰も見向きもしなくなりました。そもそも、10本倒すのに必死に練習するスポーツを子どもの遊びにそのまま取り入れたのが間違いでした。前々回の拙稿「小さなバットに大きなボール」の反省が生かされていませんでした。
一方、直径60㎝以上にもなる風船が大人気。風船は人気の遊び道具なので今までもよく利用していたのですが、今回は特大のものを用意しました。
それはバランスボールと違って風船と同じように空中に漂い、落ちてくる時間もゆっくり。また、普通の風船はキャッチするのに手で掴む感じですが、大きい風船は体に抱きかかえる感じなのです。だから、キャッチしやすいみたいです。何より、容易に捕まえられるから、周りの大人からも「上手、上手!」の声が何度もかかります。「そりゃ、気持ちよく遊べるわ。」と仕掛け人の私も大喜びで「上手い、上手い!」。
小学校、いや幼稚園の年長さんあたりから遊びの中にドッジボールが登場します。あの小さなボールを全身で受け止め、時には当たらないようにかわす人気の遊びですね。やがて、ボールは弾かれ(バレーボール)、蹴られ(サッカー)、叩かれる(野球)存在になっていきます。
「今は、私と仲良くして、しっかりと抱きかかえてほしいな。」(ボールの独り言)子ども達にはそんな声が聞こえているのかもしれませんね。
「そんなに走ると、こけて怪我するに」
部屋から部屋へ、廊下から台所へと、サーキットコースを周回するがごとく家の中を駆け回る子どもたち。見かねて出た言葉ですね。
しかし、そんな親の思いは伝わるどころか逆にレースは盛り上がるばかり。そして、「やめなさいってば」と声のトーンが上がり、最後には、「もう、いい加減にしなさい!」と目まで吊り上がります。洗濯物を畳みながらも、食事の用意をしながらも目の離せない時期の子どもたちですから、こんな出来事は日常茶飯事。
でも、本心は思い切り走ってほしいし、走っても転ばない術を身に着けてほしいし、怪我などしないたくましい身体に育ってほしいのです。だから、疲れた体に鞭打って、広い公園に連れて行って「さあ、存分に走りなさい」と子どもを放します。これでいいだろうとベンチに腰掛け見ていると、これが走り回らないのですね。家の中ではキャッキャと走り回っていたのに拍子抜けです。せっかく広い公園に来たのにと疲れも倍増。
そこで考えてみました。家と公園での違いはなぜ起こったのか。子どもたちはどんなことに喜々とするのか。
まず、ダメとかやめなさいという言葉ほど子どもたちを刺激する言葉はないということです。いけないことほど魅力的なことなのです。困ったことですが、この時期の子どもたちの特性でもあります。
そして、山あり谷ありカーブあり。ソファーにカーテン、ぬいぐるみ。次々と迫りくるシーンはゲームの比ではありません。3周目を迎える頃には脳も体もコースを熟知し、「やめなさい」の言葉すら声援に聞こえてしまうほど。
さらに、相手がいようものなら、追いかけっこの要素も加わり無類の遊びになってしまいます。
これだけの要素が整えば、ゴールのない永遠の遊びが始まっても仕方がありませんね。毎日お疲れ様です。
さて、この遊びを制するにはゴールが必要なのですが、どんなシーンを用意すればいいでしょうか。皆さんで考えてみてください。
家事で忙しくしている周りで、部屋から部屋へと走り回る子どもたち。「ドタバタ、ドタバタとやかましい。家の中では静かにしなさいって何度言えばわかるの」とイライラ感が募る場面ですね。そこで、子どもたちのレースを終わらせるために、どんなゴールを用意すればいいでしょうかというのが前回の課題。平たく言えば、どうすれば遊びをやめさせられるか、でしたね。
科学者や先生方は、「そんな時こそ子どもたちの楽しさに共感し寄り添うことが大切」って言うけれど、イライラ感爆発で共感するなんて無理。だって、ドアを開けて廊下に出て、突き当りを右に進んで隣の部屋へ。ソファーを乗り越え、テーブルの下で頭を打ち、カーテンをくぐり、座布団を踏んでこちらの部屋へ。何が面白いのか、疲れるだけだわと呆れます。
でもね、子ども目線なら、ドアの向こうはスケートリンク。右カーブは体重移動に減速が肝要。スリップと転倒に注意。ソファー越えでは滑り落ちないよう3点で体を支持。テーブルくぐりは頭上注意。這うか、屈むか、判断を誤ると時間のロス。最後の座布団は最難関。着地点は狭くバランスを崩すと海に沈没。慎重にジャンプ!
2周目、3周目になると体も慣れスピードアップ。興奮は絶頂に、大人の怒りも絶頂に。
こんなにも楽しい遊びを終わらせるなんて確かに難問ですね。そこで、こんな一言を試してください。「じゃあ、ゴールはパパ・ママの胸の中。」子どもたちは座布団を踏んだら大好きなパパ・ママの胸の中に向かって飛び込んでくるでしょう。そんな子どもを受け止め(しめしめと)抱きしめる喜び。双方大満足。あとは、畳んだ洗濯物を指さし、「これ、タンスまで運んでくれる?その後お茶碗を並べて夕飯の準備、今夜はハンバーグ。さあ、レッツゴー」
ところで、この遊びには体重移動、危険回避、3点支持、バランス感覚、身幅や逆さまの感覚、ジャンプ力、判断力など、生きていく上で必要な力がこんなにも詰まっているのです。ビックリですね。
さて次の課題は、「せっかく広い公園に連れてきたのになぜ遊ば(べ)ないの」です。
「思い切り遊ばせたいのに」と降り続く空を見上げてきましたが、今朝は快晴。早速芝生が広がる公園へ。
「さあ、思う存分遊びなさい。」と、木陰のベンチから手を振ります。
ところが、はじめこそ走り回っていたもののだんだん遊びが続かなくなってきました。「部屋の中ではあんなに走り回っていたじゃないの。遠慮することないのよ。」と拍子抜けです。そこで口をついたのが今回のテーマ。
さて、あなたが子どもだったらどんな遊びをしますか?子ども会議で提案してください。
回答1.とにかく走り回る。広いから全速力でも大丈夫。(男性31歳)
(子ども)「それ、いつまでやるの?」「どこまで走るの?」
回答2.フリスビーはどう?(女性30歳)
(子ども)「いいかも。でも家にそんなのないもん。」「当たると痛くない?」
回答3.ゴム跳びはどうかしら(女性32歳)
(子ども)「輪ゴムをつなげるのね、面白そう」「私、跳び方知らないの」
回答4.野球、野球!(男性33歳)
(子ども)「一人じゃできないよ」「グローブもないし」
回答5.断然サッカーだな(男性28歳)
(子ども)「二人でできる?」「シュートは無理だよな。ゴールがないもん」
回答6.固定遊具を探してみたらどうでしょう(女性26歳)
(子ども)「うん、行こう行こう」「前、滑り台の下でカタツムリをみつけたよ」
どうにもこうにも、大人と子どもで意見がかみ合いませんね。
さて、広い公園で上手く遊べない子どもの気持ちは想像できましたか。
まずは一緒に遊ぶことから始めましょう。子どもは追いかければ走ります。チョウやバッタを追いかけるのも大好きですね。
そして、この時期は遊び方じゃなく、楽しさをどう伝えるかが大切。「それ楽しそう、面白そう」と思わせることです。雨後の公園なら、水たまりを避けて走ったり、濡れた草の上を滑ったり、雨に濡れた紫陽花に驚いたりなどいつもと違う「楽しさ」に気付くでしょう。
公園をただの広場にするか、楽しさや面白さが溢れるワンダーランドにするか。一人で心細かったら、カタツムリやミミズ、草花や蜘蛛の巣まで応援を頼みましょう。「思う存分遊びなさい。」では子どもは困ってしまいます。
では、どんな言葉がけをして広場に連れ出しましょうか。またまた宿題です。
突然ですが「三角ベース」ってご存知ですか。野球をご存知の方は2塁ベースのない野球、そうでない方は握りこぶしくらいの軟らかいボールを投げたり棒(手)で打って走ったりする遊びと思ってください。
教室くらいの広さがあれば十分ですが、それより狭くても広くても大丈夫。場所(広場)の形は問いません。人数も決まっていません。その場にいた者全員がプレーヤー。グローブやバットも必要なし。王、長嶋が大活躍の野球をやりたくて、子どもなりに考えた遊び方でした。そう、子どものアイデアから生まれた遊び方なのです。
すべてにおいてこの適当、あいまいさでもとびっきりの笑顔で遊んでしまう子ども達。ベースが4つも置ける広々とした公園なんてそうそうあるものではなく、1個省いて三角形(本塁、一塁、三塁)にベースを置いて(実際には地面にベースの形を描いて)楽しみます。ですから空き地で十分。生えている木やベンチがあれば、そのまま一塁と三塁に変身。時に一塁と三塁がめちゃくちゃ遠くなることもありました。それも楽しかったなあ。枝に当たってボールの方向が変わることもしばしば。バットがなければ落ちている棒切れで、それもなければ手打ちで。下級生が打った後間違って三塁に走れば、そこからはランナーは逆回りになる特別ルールも。途中で「入れて」と来れば、即メンバー入り。守りのポジションは適当。打ったボールを一塁手に投げずに打者の背中に当てたら「アウト」なんてルールまで作り出します。だから、この「三角ベース」にはローカルルールがいっぱいあるようです。こうして全国津々浦々、野球を楽しむ姿があちこちで見られました。
何かを楽しもうと大人では考えられない軟らかい頭で遊びを創り出してしまう子ども達。そのエネルギーにはホント驚かされます。
子どもを公園に連れてきて、「さあ何をして遊ぶの」と言ったとき、あなたはどんな遊びを思い描きましたか。あなたのよく知るほぼ完成された遊びを描いていたならば、子どもはつまらない顔をするかもしれません。遊びの文化が未開発の幼児ならなおさらです。
完成とは程遠いところから遊びを創り始める子ども達。喜々とした笑顔にするためには柔らかな思考をくすぐる手立てが必要になりますね。
「そんなの難しい」って?大丈夫、あなたも子どもの頃があったのですから。
大人に近づけようと思わず、あなたから子どもに近づいていってください。「それ、おもしろい遊び方ね、ママにも教えて。そして一緒に遊ぼ。」ってね。
昨年の秋、御在所岳登山に出掛けた折の話です。その日は天気も良く、沢を渡ったり岩場を乗り越えたりする変化に富んだ裏登山道を3時間ほどかけて登ります。
登り始めて1時間、紅葉に見とれながら進んでいくと前方に園児らしき男の子と小学校高学年の姉、その母のご家族が見えてきました。ちょうど私の体力も限界に近づいていたので、渡りに船と園児に合わせてペースダウンすることにしました。リンゴ飴を取り出し同行のお願いをすると、小さな手で塩飴を返してくれ、たちまち僕たちは友達になりました。しかし、これが大変なことになるとはその時はまだ気付いていませんでした。
男の子は岩場の続く登山道を楽しむかのように、小さな岩は飛び越え、大きな岩は隙間をすり抜け、隙間がなければよじ登り、その姿は小さな忍者そのもの。しかも、よじ登った岩をわざとずり落ちる「逆さ滑り台の術」も使うのです。登山道の逆走なんてありえないと唖然とする私。その度に、してやったりのどや顔に振り回される母、姉、そして私。時々使う登山道を外れる「道変の術」に悩まされつつ、同行の契りを交わしたこともあり、必死に追い掛けましたが、もうそのペースにはついていけません。しかしそこは小さな子。様々な術を使うものの長続きはしません。その度に疲れて座り込んでしまいます。母はおやつで釣ったり、根気よく説得したりして登山を再開させるも、忍者はたちまち燃料切れ。その繰り返しに私たちは完全にペースを乱されてしまいました。登山道ですから所々に鎖場もあります。そんな時には我が子のすべての術を封印させ、慎重に進ませなくてはなりません。いやはや母のエネルギーには頭が下がります。
さて、ようやく国見峠に到着。頂上まではもう少しです。一定のリズムで登るのがセオリーなのに、真逆の登り方ですから相当疲れているだろうと思い、「ゴールはもうすぐだよ。がんばろうね。」と声をかけると、「死んだふり」の術を解き、一目散にすっ飛んでいきました。
後のことを考えて余力を残しておく、そんな大人に比べれば、その時その時を全力で遊び、目いっぱい楽しむ姿はうらやましい限りです。
男の子は駆け上がった先で私を待ってくれていて、最高の笑顔で迎えてくれました。しんどかったけど、その笑顔で疲れがフワッと消えていきました。母のエネルギーもこうした笑顔から生まれてくるのですね。少なくとも3時間、途中くたびれることはあっても、様々な忍術を駆使して登り切った小さな忍者とお母さんに「あっぱれ」です。
梅雨の晴れ間の日曜日。近くの公園を訪ね、子ども達の様子を見てきました。
やはり人気があるのは滑り台ですね。多くの子ども達が滑っては階段を上っていきます。親御さんたちもその様子を目を細めて眺めています。しかし、子どものある行動で雰囲気が変わりました。滑り終わった子どもが滑り台を登り始めたのです。怪訝そうな顔をする親御さんを横目に、滑り台を登っていく子と下りる子とがじゃんけんを始め、遊び方がガラッと変わってしまいました。その顔は喜々として楽しそう。
ブランコに目を移すと、子ども達が気持ちよく漕いでいます。行って戻ってくるだけの単純な動きなのですが、その動きに身体を委ねることの心地よさは大人になった今も体が覚えていますね。
ジャングルジムはどうでしょう。考えてみると、滑り台やブランコに比べて遊び方が決まっていないように感じるのは私だけでしょうか。とりあえずてっぺんまで登って公園を眺め渡してみる。その後はと言うとあまり記憶がないのです。皆さんはどのようにして遊んでいましたか?公園の子ども達はどうでしょう。てっぺんに登った子は下の子から逃げているようです。なるほど鬼ごっこでしたか。別の子は狭い四角い枠をくぐりぬけています。上下左右に進むだけでなく、ひっくり返ったりもしています。鬼ごっこ組は、ジャングルジムを上ったり下りたり、はたまたジャングルジムを挟んでにらめっこ。おっと、ブランコの方に逃げました。逃げる範囲は公園全体なんだ。
公園の様々な遊具は、有り余る子ども達の遊び心をくすぐり、様々な動きの体得に力を発揮してくれます。だから、限られた動きしかないブランコでも、靴を飛ばしたり立って漕いだり、ときに振れを利用してジャンプして降りたりしていろいろな動きを作ってきました。まさか、鎖をぐるぐる巻いて、回転させるとは制作者も想像しなかったでしょうね。でも、それらは危ないからと制限がかかりました。仕方のないことかも知れません。その点ジャングルジムは制限がなく、いろいろな動きが楽しめる遊具なのでしょう。
色々な遊具で楽しめる公園。安全第一ですが、動き(遊び方)を決めずに楽しませてあげてください。子どもは遊びの天才なのですから。
「ハンカチで拭きなさい。」とよく叱られたものです。そう、手洗いの後、拭く物がなく手をブラブラして水気を振り落していた時のことです。振ってズボンで拭くのが主流だった大昔の話です。
こんな昔話を思い出すきっかけとなったのは、ある木工教室に参加したことでした。親子が使うのは金づち。釘を所定の場所にセットし、倒れないよう指でつまんで支え、その頭をめがけて金づちのヘッドを振り落ろす。しかし、釘は倒れるわ、斜めに入り込むわ、はたまた自分の指を殴打するわで大変難しい作業です。
さて、この作業を見ていて気になったのは金づちの使い方。その動きが包丁に似ていたのです。包丁は肘、手首、指先まで固定し力を包丁に伝えます。しかし、金づちは最初に肘が動き、続いて手首、そして指先へと順に力が伝わり最後に金づちのヘッドが動きます。上手くなると、最後に手首の動きを止めることでより効果的に金づちのヘッドに力を伝えます。難しいようですが、この動きは手を洗った時に水気を振り落とす時の動きにそっくりなのです。小さい時から経験している動きなのですが、金づちを持つと包丁の動きになってしまい、叩いても叩いても釘は刺さってくれません。つい、最近の主流はハンカチだからなぁと昔の愚行を肯定してしまい、恥ずかしくなりました。
経験は積み重なって、身体を思い通りに操る力となります。
しかし、子ども達が積み重ねる経験が、その数も種類もだんだん乏しくなってきているのが気になります。
高い所にある荷物を取ろうとするとき、人はつま先立ちになり、片方の手だけを伸ばし、もう片方はぐらつく身体を支えるために壁に添えますね。こうして知らないうちに最高点に手を伸ばす時の骨の構造や3点支持の感覚をつかんでいきます。その時、誰かがその荷物を取ってしまえば、大事な経験を奪ってしまうことになります。
だから、「これはいい経験になるかもと思ったら、静かに見守る姿勢が大切ですね。」とよく話すのです。そして、我慢できずに手や口を出してしまう親御さんには、「アドバイスは最低限にね。」と話しているのですが、いつも「それが難しいんですよ。」と言われてしまいます。
難しい「それ」って、いい経験かどうか見極めることなの、見守ることなの、アドバイスの言動なの、機会があったら親御さんと話し合ってみたいものです。「全部よ、全部」と言われそうですが。
我が家に「電動鉛筆削り」がやってきたのはもう60年以上前の話。それまではくるくる回すハンドルのついたもの、その少し前までは剃刀か小刀でした。だから、削り方がみんな違っていました。さらに木の部分を削っていくと芯が出てきて、その先をいかに細く仕上げるか。その角度にも個性があって、細長いのやら短いのやら、色々あって楽しかったです。
でも、鉛筆削りで削った鉛筆はどれも同じ形。刃物を使うという緊張感もなければ根気も必要なし。ただ回すという単純作業が伴うだけ。電動になると、もはや体力も必要なし。ただ穴に差し込むだけ。
ある日公園で仲良く遊ぶ親子連れを見ていて、あることに驚き目が点になりました。
シャボン玉遊びの場面でした。所々に穴の開いたプラスチック製の筒を石鹼水の入った容器に差し込み、腕で振り回してシャボン玉を発生させる今どきのおもちゃかと見ていると、なんとスイッチ一つでみるみるシャボン玉が飛び出てきます。よく見ると、プラスチック製の筒には乾電池が入っているらしく、「電動シャボン玉発生器!」ドラえもんならそう叫びそうな道具でした。
思わず「そりゃないでしょう、お父さん。」と声を掛けそうになりました。
電池や充電器がおもちゃの世界に入り込んでから、子ども達は変わってきました。 本来、電気って足腰が衰えていくお年寄りを支えるために使われるものでしょう。電動シニアカー然り。扇風機、テレビや照明器具のリモコンなどもそうです。元気溢れる子どもなら歩き、うちわで扇ぎ、立ち上がってチャンネルボタンを押したり、スイッチをひねったりできるはずです。
昔から人気のある三輪車ですら、電動の車にそのシェアを奪われてきているようです。あの百円玉を入れてしばらく動いてくれるデパートの屋上にある遊具ですね。三輪車はペダルに届くまでは足漕ぎで地面を蹴ることで足腰の鍛錬にもつながりますし、ペダルに届くようになると足腰はもちろん、左右の足を使って、代わるがわる力を入れるタイミングの取り方も学べます。
残念ながら、楽をすることで失うものが多いような気がします。
割れるかどうかを心配しながら、ゆっくりゆっくり息を吹き込んだシャボン玉。
少しの揺れも許されないと、かえって緊張して手が震えた線香花火。
どれも、子どものときに味わいたい経験ですね。 巷には楽しそうなおもちゃがいっぱいですが、どうか乾電池やバッテリーに負けない選択をお願いします。
「またやってしまった。」「なんでこうなるの。」「私が悪いわけじゃあ・・・」
上手くいかないのは、大人も子どもも同じ。降りかかる不幸を声高に叫ぶ大人もいれば、動きを止めて涙目になりじっと耐える子どもも。人生に辛いことは付きものですが、その表現は多様で複雑です。
しかし、大人はともかく小さな子どもに失敗や挫折はなるべく味わわせたくはありません。かと言って、失敗や挫折を体験しなければ、それらを乗り越えるすべを学ぶ機会を失ってしまいます。
成功と失敗の割合ってどれくらいがいいのでしょう。
ある遊びの会で、小さな子どもが一緒に遊ぼうとやってきました。
手にはプラスチック製のバットとおにぎりくらいのプラスチック製のボール。ボールを渡された私は出来るだけ打ちやすい球をそろりとストライクゾーンへ。しかし、空振り。
最初は笑顔でボールを拾いに行っては私に返すも、何度も空振りを繰り返すうちにだんだん不機嫌に。そして、とうとう最後は怒り、泣き出す始末。楽しい遊びがとんでもないことになってしまいました。
その子をなだめながら遊び道具が置いてある倉庫に目をやると、凹んだビーチボールを発見。すかさずそれを膨らませ、「これを打ってみようか。」と私。なんと、これが大正解だったのです。どこに投げてもバットに当たるわ当たるわ。 さっきまでの涙目はどこへやら。
それを見ていた子ども達が、私も僕もと順番待ちの列が出来てしまいました。
やはりバットに当たらないと、この遊びは成り立ちません。三振を取る野球とは違う遊びなのです。なのに、バットと来ればあの小さなボールと信じて疑わない大人(私も)に「喝」ですね。
最も、おもちゃ売り場を見てもミニバットとミニボールがセットになって売っているので、その組み合わせが当たり前と思うのも無理はありません。小さい子に、あんなので当たるわけがないのに。
もともと小さなボールをバットで打つのは大人でも難しいところ。だから、最初から大きなボールを使うなどして、ちゃんとバットに当たるという配慮が必要でした。
それぞれの遊びのもっとも面白いこと、今回なら振ったバットにボールが当たるということをちゃんと経験させることが大切ですね。
さて、最初に考えてもらった成功と失敗のバランス。難しいけど、10回中1回か2回くらいは失敗する、それくらいでいかがでしょうか。
テレビのスイッチ、リモコンにビデオ、照明のスイッチ。小さな子どもはスイッチが大好きですよね。今日はスイッチ(ボタン)を触って大変なことになった1年生のお話を聞いてください。
小学校に入学して間もない頃、学校から帰るのを見守るために担任の先生が家の近くまで送っていくことがあります。まずは道路の横断。歩行者用の信号機があるので、ボタンを押して信号が変わるのを待つよう教わります。信号が青に変わったのを見て、左右を確認して手を挙げて渡ります。
その先には踏切。その日は電車が通過することもなく遮断機も上がっていたので、先生とともに踏切の向こう側へ。そしてそれぞれの家に向かって帰っていくのでした。
しかし、何日かして子ども達だけで帰ることに。事件が起きたのはその時でした。踏切の遮断機が降りていたのです。
もちろん、電車が通り過ぎて遮断機が上がるまで待つよう先生に教えられてはいたのですが、待ちきれなかったのでしょうね。足を止めたすぐ横にボタンがあるのを見つけて押してしまい、大変なことになったそうです。
横断歩道と踏切にある二つのボタン。どちらも早く渡りたいからと押ししてしまった子ども達を責めることは酷ですね。
3塁に走っちゃダメ(野球)、ボールを前に投げちゃダメ(ラグビー)、3回以内で相手に返すこと(バレーボール)、2回ついたらダメ(バスケ)などなど。これはいいけど、これはダメというルールに、これからいっぱい出会うと思います。
わけもなくグルグル走り出したり、ピョンピョン跳ね出したり、と思えば滑り台を駆け上ったり。何が面白いのと思うのは大人だけで子ども達は最高に面白いのです。本当は自由に思うままに体を動かすことが一番なのです。
まだ制限のない今のうちに子ども達に思いっきり体を動かす楽しみを味わわせてやってください。理屈のない楽しさが味わえるうちに。
最後に、いろいろな制限のある泳ぎ方。でも、競技名は「自由形」です。ほとんどの人がクロールで泳ぐけど、やっぱり「自由形」。何でもあり、何の制約もないこの競技。どんな泳ぎ方が出てくるかと心躍るのは私だけでしょうか。発想も体動かしももっと自由であってほしい、そんな思いで書いてみました。ただ、ボタンの押し間違えだけは早いうちに教えてあげてくださいね。
小学校1年生の子と一緒に牛乳パックを使って風車を作りました。 まだハサミを上手に使えないのでしょう、普通の紙より分厚い牛乳パックを切るのに苦労しています。両手で持ってうんうん言いながら切る子もいれば、ハサミの先の方で切る子、結局切れないのですがそんな子もいます。何事も経験と思い、「刃を大きく開いて、根本の方で切るといいよ」と見本を見せながら子ども達の間を回ります。
小学校に上がるまでに、機会をとらえて様々な経験を積ませてくださいね。ハサミだけでなく、箒で掃いて塵取りでごみを集めたり、雑巾を絞って床を拭いたり、また、雨の日は傘を広げたり、畳んだりなど勉強以外にたくさんやらなければならないことがありますから。
さて、風車の続きを。次は針金にビーズやストローをつけ、切り取った牛乳パックの羽根を取り付けていきます。最後に私が針金を曲げて、竹の棒に取り付けました。 出来上がった風車を嬉しそうに受け取ると、早速その場でくるくると回っています。うまく空気を捉えられなくてなかなか回らずがっかりしていると、教室の壁の扇風機を見つけ、先生に「回して、回して」 とせがむ子ども達。扇風機の風を受け、風車は気持ちよく回っています。多くの子どもが風車を高く掲げ、一斉に扇風機に向かう姿は絵になります。うん、風を受けて回るのが風車ですから本来ならばこの姿で良しですね。
しかし、そこは大人と子どもの違うところ。もっと早く回したいわけです。
だから、「運動場に行ってもいい?」と先生にせがみます。
もうお分かりと思いますが、手に風車を持って力いっぱい走るとくるくる回るのです。風を受けるのではなく、風を起こしに行く子ども達のエネルギーには驚かされます。全力で汗びっしょりになりながら実に楽しそうに走り回っています。
運動会の徒競走、風車を持たせて走らせてみてはどうでしょう。嬉々とした笑顔溢れる徒競走になると思いませんか。「あなたの風車がビュンビュン回ってかっこよかったよ。」と夕飯の時の会話が弾むかもしれません。
また、風車を持って走る練習をしたら、知らず知らずの間に走力アップも期待できるかも。体育の時間にやってくれないかなあ。
なぜこんなにも印象深く頭に残っているのでしょう。確かに「ドッジボール」も多く遊んだ気はします。だけど、みんなで列を作って靴のつま先でコートを描いたことや突き指をしてしまったことは思い出せるのですが、ドキドキ感はそれほどでもなかったような気がします。ボールとコート、それにある程度の広い平地が必要でしたから、条件が整わないこともあったのでしょう。ところが、「かくれんぼ」も「鬼ごっこ」も何も準備も必要なし。そして、隠れる、逃げるといった特段難しい技を必要としない点、隠れる場所、逃げ回る空間は工夫次第でどれだけでも作ることができる点など、どの子にとっても一番身近な遊びだったのですね。だからこんなにも記憶に残っているのでしょう。
鬼「もういいかい」(声がする方に逃げたから、すぐに見つけられるぞ)
「まあだだよ~」(さて、どこに隠れようかな)
鬼「もういいかい」(はやく隠れて返事してくれ~)
「・・・・・」(ここなら絶対みつかりっこないな)
鬼「・・・・・」(うん?返事がないからもうさがしてもいいのかなあ)
わずか数分の間にこれだけの駆け引きですが、「かくれんぼ」の本番はここから。次第に近づいてくる鬼の足音にドキドキし、息を殺して身構えます。だけど運よく鬼が通り過ぎてからは、長い独りぼっちの時間。耐えきれずに、カサカサと音を立てて鬼の気を引くも反応なし。10分もすると、「早くみつけてくれ」と自ら飛び出していくことも。 このような経験をしようと思うと、ゲーム機の中では狭すぎるし、体を使った工夫もできなければ、本物のドキドキ感も少ないのではないでしょうか。
さあ、子ども達よ、暖かくなったら外で元気よく「鬼ごっこ」と「かくれんぼ」だよ。お父さん、お母さんも一緒にドキドキ感を味わってくださいね。
電気で動く炊飯器や冷蔵庫、エアコンなどに慣れた子ども達にとって、人の力や炭、自然の力を生かした昔の道具に興味津々。
その中でいちばん人気があったのは、羽釜や火鉢ではなく「フィルムカメラ」でした。カメラにフィルムを装てんして使うカメラ。小窓から被写体をのぞき、構図を決めて「カシャ」っとシャッターを切るあのカメラ。これをお読みの若い保護者の方には何をそんなに興奮しているのと言われそうですね。
でも、子ども達はこれがお気に入り。その姿を観察していると人気の理由がみえてきました。カメラを手に取った子ども達は、小窓をのぞき込んで友達の方に向けます。向けられた子どもはポーズをとってカメラの方を向きます。今のように撮った写真がすぐに見られないのに、撮った方も撮られた方もなぜかニコニコし、はにかんだ表情は素敵な笑顔でした。
他の道具の反応はどうだろうと見ていると、見たことのない昔の道具に関心を寄せるものの、先ほどのような素敵な笑顔は見られません。いや、もう一か所ありました。それは「ダイヤル式黒電話」と「ハンドルを回して使う電話」。
たまたまこの二つが隣同士に展示してあったのですが、この二つで仲良く素敵な笑顔でおしゃべりする姿を見ることができたのです。 「カメラ」と「電話」。共通点は何だろうと考えていると、「そうか、相手がいるんだ。」と気が付きました。
そこで浮かんだのが、友達の家を訪問し一緒に遊ぶのかと思いきや別々にゲームに興じる子どもの姿でした。
「ゲーム機の向こうには笑顔をかわせる友達はいないよ。一緒に遊んだら。」と言いたくなりますね。 大人はいろいろあって相手との距離感を調整しますが、子どもって本能的に相手を見つけて近づこうとするのですね。そこに、笑顔や会話、衝突が生まれ成長していくものだと思います。
私は、そんな関係を深めていくスポーツの力を信じている一人です。 小さな子は、まずは友達と群れて遊ぶことですね。 近くの公園や幼稚園の園庭から、笑顔いっぱいにワイワイ言いながら群れる子どもの姿を見ると、大丈夫、大丈夫とホッとしてしまいます。
信号で停まると、カラスが目の前の横断歩道を渡っているのです。片側2車線、横断歩道の長さは15メートルほど。通勤時間帯のため、周りにはたくさんの車。そんな中を跳ねるように左から右へと横断歩道を渡るその姿に、「頭の良いカラスだから、そんなこともあるわな。朝からとんでもないものを見たわ。」と思う反面、「そんなことあるはずはない。何かの間違い。」と頭は大混乱。「飛べないカラス?」「突然変異の天才カラス?」いずれにしても、賢いカラスが現れたものです。
学校の先生にその話をしてみたら、
「あるかもしれませんね。」と驚く様子もなく、こう続けてくれました。
「カラスは実践を通してどんどん賢くなっています。でも今の子どもはあの四角いタブレットの中でしか体験できなくなっているのです。近いうちにカラスに追い抜かれますよ。」と。また、この夏は猛暑のため運動場に出て遊べない日も多く、休み時間なのに教室でタブレットと向かい合う時間が多かったそうです。外遊びの経験が格段に減ってきているようですね。
ところで、読者の中には夏休みの宿題だった読書感想文で悩み苦しんだ人はいませんか。でも今はAIに尋ねると本人に代わってすらすら感想文を書いてくれるそうです。先ほどの先生も、
「親子合作の工作ならともかく、AIが作った読書感想文にどんなコメントを書き添えたらよいか悩みますね。コメントもAIに頼みますか。」と笑っておられました。
また、AIに尋ねるとなんでも丁寧に答えてくれるそうで、
「人に尋ねたり、ページをめくって探したり、そしてそれらを自分の言葉でまとめたりしなくていいのですからね。」と先生もお手上げ状態。
読者の皆さんは、様々な経験や苦労、失敗を重ねながらここまで生きてこられたことでしょう。中には「いや、まだまだ苦労や失敗の連続ですわ。」という方も。
子ども達には、丸投げや疑似経験しかできない四角い画面から抜け出して、多くのことに挑戦し、失敗し、学ぶことの大切さを取り戻してほしいと真剣に思っています。
「カラスに負けるな!AIに頼るな!」って言い過ぎでしょうか。
