当センター入所児の主要疾患である、脳性麻痺、ペルテス病、二分脊椎について説明します。
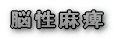
脳性麻痺は、こどもの脳に脳梗塞が生じたものと考えるとわかりやすいかと思います。脳性麻痺と成人の脳梗塞との大きな違いは、脳性麻痺では発達途上の脳にダメージを受けるということです。脳性麻痺の発症に関連する因子としては未熟児、低酸素脳症、新生児黄疸の三つが主要なものとされてきました。また脳の障害が胎生期から新生時期(生後4週まで)までの間に生じたものだけを脳性麻痺と定義することになっており、それ以降に生じた脳障害に基づく麻痺は、厳密には脳性麻痺とは呼べません。しかし一般には言葉の定義が曖昧なまま用いられていることもあります。画像診断では脳質周囲白質という運動と関連の深い領域にダメージが認められることが多く、患児の多くは運動発達が遅れていることで発見されます。麻痺という表現が用いられていますが、手足のどこかが全く動かせないということはまずありません。多くの脳性麻痺児は運動に必要な正しい姿勢がとれなかったり、正しい運動パターンでの運動が苦手だったりします。また筋に異常な緊張があるため、長期的には関節の可動範囲に制限が生じたり、関節そのものが変形してきたりします。脳そのものに対する治療法はありませんが、麻痺が発達に及ぼすこれらの影響を最小限にするように訓練が行なわれます。また装具療法や手術も行われます。脳性麻痺にはアテトーゼ型といって不随意運動が目立つタイプもあります。運動障害に加えて知的障害や、てんかんの合併もみられます。このように脳性麻痺といっても患児の状態は様々で、状態にあわせた治療が必要になります。
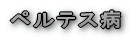
ペルテス病は小児の股関節が侵される疾患です。原因は血流障害による大腿骨骨頭の壊死であることがわかっています。しかし、なぜ血流障害が発生するのかわかっていません。好発年齢は4〜8歳位で、男女比は9:1と多くを男児がしめます。症状は疼痛や跛行ですが、症状が穏やかであることも多いため、発症から数ヶ月間ペルテス病と診断されずにいることも少なくありません。ペルテス病の自然経過を見ると、壊死した骨頭が体内で吸収され、レントゲン上は次第に骨が消えていくような経過を取ります。しかし一年程度観察していると、吸収されていた部分の骨が再生してきます。発症から2年程経過すると骨頭の大部分に再生が見られます。したがって治療は成人の大腿骨骨頭壊死とは異なり、保存療法を基本としています。保存療法を行ううえでの基本的な考え方は二つあります。一つは股関節の免荷です。経過中に関節破壊がひどくならないようにするためです。もう一つは臼蓋側と大腿骨の位置関係を正常に保つことです。こうすることによって、元どおりの球形に近い骨頭が再生しやすくなると考えられています。治療には装具を用います。初めのうちは股関節を大きく開いた形で逆V字型の装具をつけます。この段階での移動手段は車椅子になります。経過が順調であれば股関節を開いたまま歩けるように歩行装具へ移行します。当センターを始め多くの施設ではタヒジャン型と呼ばれる装具が使用されています。装具治療が終了してからも、医師から生活指導を受ける必要があります。骨頭壊死が広範囲の場合には内反骨切り術という手術療法が行われることもあります。
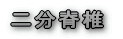
新生児の腰背部に髄膜瘤というコブが認められることがあります。これが二分脊椎という先天異常です。二分脊椎に発生率には人種や地域により差があることがわかっていますが、発症原因は不明です。コブの本態は脊髄の神経組織であり、下半身に高度の麻痺を認めます。麻痺に対する根本的な治療はなく、下肢の変形を防止するための装具療法や訓練が行われます。多くの児で膀胱直腸障害が認められますので、排尿排便の管理も必要になります。手術で人工肛門を作らないといけない場合も少なくありません。また水頭症の合併率も高く、この場合はシャント手術という手術が必要です。これらの障害をもらさず上手く管理していくことが大切です。
![]()