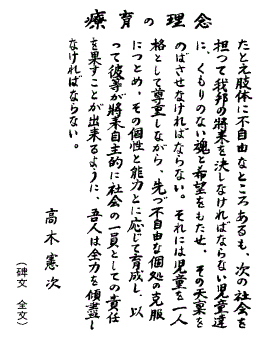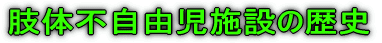
日本における肢体不自由児施設の原型は、ドイツの身体障害児のための施設であるクリュッペルハイムとされています。肢体不自由児施設の生みの親とも言われている東京大学整外科名誉教授・高木憲次先生が、クリュッペルハイムを訪れた後の1924年(大正13年)、国家医学雑誌に「クリュッペルハイムに就いて」という論文を発表し、本邦における同様の施設の必要性を説き、並々ならぬ努力の結果、1942年(昭和17年)5月に東京に整肢療護園が開設されました。この高木先生の社会医学的視点や教育から社会参加に至る基本的な考え方が、肢体不自由児施設の全国における設置に大きく貢献することになります。
| 高木憲次先生 |
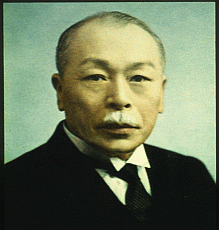 |
1947年(昭和22年)12月に児童福祉法が制定されましたが、高木憲次先生の尽力により、第43条の3に「肢体不自由児施設は上肢、下肢または体幹の不自由な児童を治療するとともに、独立自活に必要な知識技術を与えることを目的とする施設とする」と記載され、肢体不自由児施設が法的、制度的に正式に位置づけられました。整肢療護園は、1945年(昭和20年)3月9日の東京大空襲で消失しましたが、1951年(昭和26年)に、児童福祉法に基づく肢体不自由児施設・整肢療護園として再建され、現在の心身障害児総合医療療育センターの基礎が作られました。
開設当時の整肢療護園(東京都板橋)
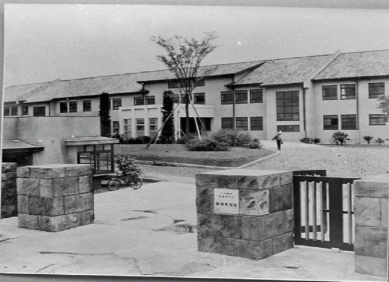
しかし、法律に位置づけられたからといって直ちに全国各地に設置されるいう訳にはいきませんでした。そこで、高木先生は厚生省の依頼を受けて療育チームを編成し、1949年(昭和24年)12月から1951年(昭和26年)11月まで、茨城県水戸市を振り出しに九州、四国、山陰、東北、北海道、関東、東海地方など全国の各都道府県に赴き、療育相談や講演を行って事業の広報に努めました。その結果、全国各地に肢体不自由児施設が設置されていきますが、全国の都道府県全てに設置されたのは、さらに10余年後の1963年(昭和38年)でした。
日本全国に設置された翌年の1964年(昭和39年)に全国肢体不自由児施設運営協議会(通称「運協」)が設立され、同年に協議会により全国肢体不自由児施設施設長・事務長会議が初めて開催されました。以後毎年、同会議において全国の施設長・事務長が集い、厚生労働省の障害福祉関係の方々も同席の上、肢体不自由児施設における障害児への療育や運営に関することなど、さまざまな課題について議論がなされています。
|
療育の碑 |
|
 |
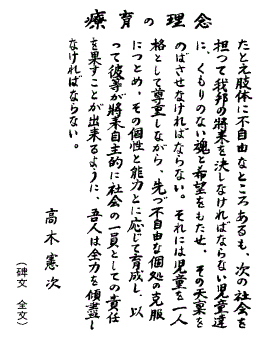 |
「療育とは、時代の科学を総動員して不自由な肢体を出来るだけ克服し、それによって幸いにも恢復したら『肢体の復活能力』そのものを(残存能力ではない)出来るだけ有効に活用させ、以て、自活の途の立つように育成することである。」(昭和26年 療育第1巻 第1号)
※引用
「肢体不自由児施設の原型」佐竹孝之(別府発達医療センター顧問)など
![]()
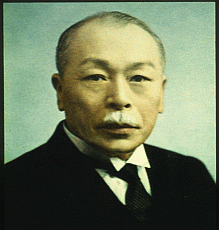
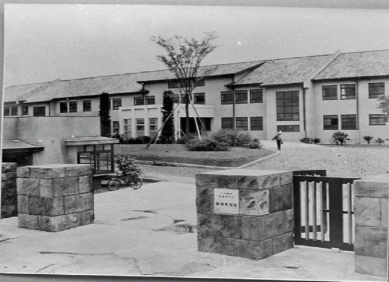 しかし、法律に位置づけられたからといって直ちに全国各地に設置されるいう訳にはいきませんでした。そこで、高木先生は厚生省の依頼を受けて療育チームを編成し、1949年(昭和24年)12月から1951年(昭和26年)11月まで、茨城県水戸市を振り出しに九州、四国、山陰、東北、北海道、関東、東海地方など全国の各都道府県に赴き、療育相談や講演を行って事業の広報に努めました。その結果、全国各地に肢体不自由児施設が設置されていきますが、全国の都道府県全てに設置されたのは、さらに10余年後の1963年(昭和38年)でした。
しかし、法律に位置づけられたからといって直ちに全国各地に設置されるいう訳にはいきませんでした。そこで、高木先生は厚生省の依頼を受けて療育チームを編成し、1949年(昭和24年)12月から1951年(昭和26年)11月まで、茨城県水戸市を振り出しに九州、四国、山陰、東北、北海道、関東、東海地方など全国の各都道府県に赴き、療育相談や講演を行って事業の広報に努めました。その結果、全国各地に肢体不自由児施設が設置されていきますが、全国の都道府県全てに設置されたのは、さらに10余年後の1963年(昭和38年)でした。