東紀州対策局 紀北地域振興プロジェクト
TEL:0597-23-3408 / FAX:0597-23-3422
e-mail:kodo@pref.mie.jp
TEL:0597-23-3408 / FAX:0597-23-3422
e-mail:kodo@pref.mie.jp
|
東紀州対策局 紀北地域振興プロジェクト
TEL:0597-23-3408 / FAX:0597-23-3422 e-mail:kodo@pref.mie.jp |
||
| TOP >
イベント > 薬草三昧 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| ■ 会場アクセス |
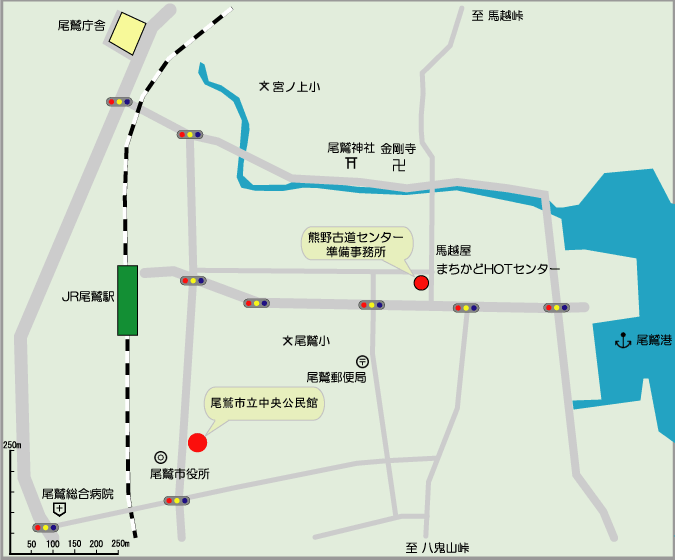 |
| ■ お問い合せ先 |
〒519-3605 三重県尾鷲市中井町12番14号 三重県地域振興部東紀州活性化・地域特定プロジェクト尾鷲市駐在 担当者:横山、服部 電話番号:0597−23−3408 FAX番号:0597−23−3422 e-mail:kodo@pref.mie.jp |
| << 戻る | ||