

三重県内の身体障害児とくに当施設の専門領域である肢体不自由児の動向について、平成18年(2006年)現在の身体障害者手帳所有状況をもとに調査しました。当施設において、昭和59年(1984年)、平成7年(1995年)にも同様の調査を行っていますので、約10年ごとの変化についても比較・検討し言及しました。ただ、最近は個人情報保護条例などの法規制などにより、詳細な情報の収集が困難なことから、充分な比較・検討ができない事項も少なからずありましたが、出来る限り分析を行い、グラフを中心に報告しました。
平成18年4月現在、三重県における身体障害者数は、68,491名で、18歳以上(以下「者」とする)は67,117名(98.0%)、18歳未満(以下「児」とする)は1,374名(2.0%)でした。
このうち「肢体不自由」は38,482名で、全身体障害者の56.2%でした。「肢体不自由」のうち「肢体不自由者」は37,600名(97.7%)、「肢体不自由児」は882名(2.3%)であり、いずれも「児」の占める割合は2%程度でした。
全身体障害児における男女比では、男児57.6%、女児42.4%と男児に若干多くみられていました。
等級別割合では、1級および2級の重度障害児が約80%を占めていました。これは、必ずしも三重県における障害児の中で重度障害児の占める割合が実質的に多いということを示しているわけではありません。1・2級など障害程度が重ければ重いほど授与される経済面を中心とした福祉的・医療的援助が大きく、等級程度が下がれば下がるほど福祉的援助が小さいため、たとえば5、6級を取得しても障害者(児)として認定されるのみで、受けられる援助が少ないことから、障害者本人はもちろん障害児の保護者の方も取得を希望されないことや医療・福祉関係者も取得を勧めないことなども要因のひとつと考えられます。
次に当施設において関わる機会の多い、肢体不自由児を中心に述べます。
全身体障害児(1,374名)のうち肢体不自由児(882名)は、64.2%と肢体不自由児が6割以上を占めていました。
肢体不自由児数においては、昭和59年(1984年)、平成7年(1995年)、平成18年(2006年)の調査では、以下のような経年変化を示しており、少子化の時代背景を考慮すれば、むしろ増加傾向にあると考えられるかもしれません。
参考に三重県における出生数の経年変化を下図に示しますが、明らかに減少傾向が続いています。2005年には出生数が16,120名となっており、脳性麻痺の発生が出生1,000に対し2名程度と言われていることから、最近の三重県における1年間の脳性麻痺児の出生数は、30名程度と推定されます。
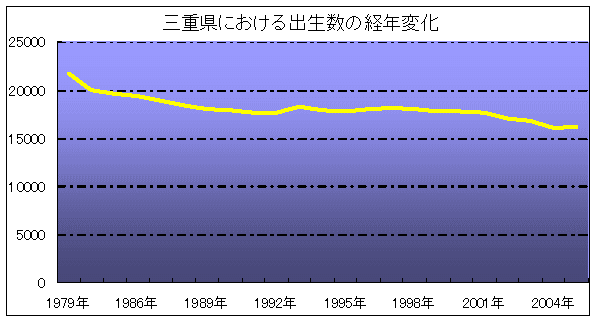
肢体不自由児における疾患別割合では、脳性麻痺を含めた脳性運動障害が73.4%、先天性奇形5.3%、二分脊椎3.9%、筋ジストロフィーなどの神経筋疾患1.8%、分娩麻痺0.7%となっています。
※脳性運動障害には、脳性麻痺はもちろん水頭症、小頭症、ダウン症候群などの脳神経障害による運動障害を含んでいます。
昭和59年(1984年)、平成7年(1995年)との比較では、二分脊椎児の占める割合が20年前と比較し若干増加傾向がみられている以外、疾患別割合にはほとんど変化がみられず、脳性運動障害が70%以上を占めています。
肢体不自由児の男女比では、全身体障害児における男女比とほぼ同様の傾向を示し、男児57.7%、女児42.3%と男児に若干多くなっていました |
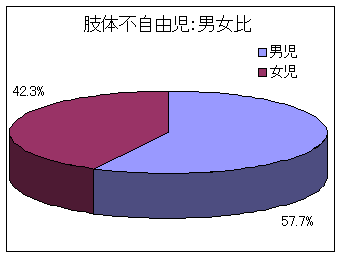
|
その他の疾患別の男女比では、脳性運動障害においては、男児にやや多く、全肢体不自由児とほぼ同様の傾向を示していました。筋ジストロフィー症などが多くを占める神経筋疾患においては男児が約70%と多くみられていますが、先手性奇形や二分脊椎では若干女児に多い傾向がみられており、分娩麻痺での男女比はほぼ同じでした。
|
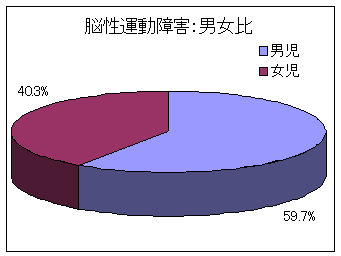
|
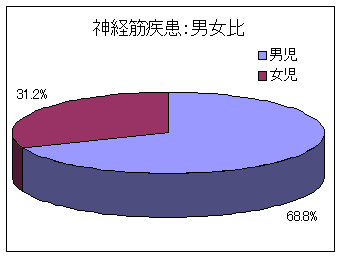
|
|
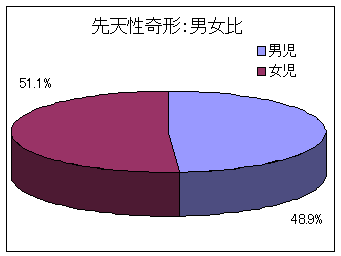
|
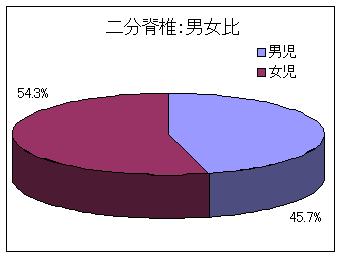
|
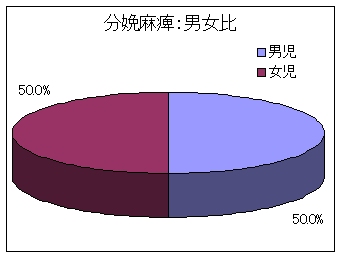 |
※昭和59年(1984年)、平成7年(1995年)と比較しましたが、これら疾患別の男女比でもほぼ同様の傾向がみられています。 |
肢体不自由児の等級別割合では、前述のように1級から2級の重度障害児が79.9%とほぼ80%を占めていましたが、昭和59年(1984年)では65.7%、平成7年(1995年)では77.3%であり、20年前と比較して明らかに障害程度が重度の手帳を所持している肢体不自由児が増加しています。
身体障害者手帳の取得時年齢については、脳性運動障害に関しての昭和59年(1984年)、平成7年(1995年)の調査によれば、1級、2級の重度の障害児が3級〜6級の中軽度の障害児よりもかなり早く取得していました。これは、重度障害児ほど診断の早期確定が容易なこともありますが、保護者の障害の受容が早いことや日常生活用具や装具などが必要になる場合が多いことなどが大きな要因と考えられました。
※平成18年(2006年)の身体障害者手帳では、取得時月齢の分析が困難であったため、今回は検討しませんでした。
![]()
![]()