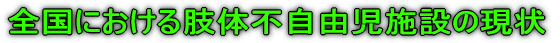
医療保険制度改革や診療報酬改定などにより、医療機関の運営・経営面における環境は悪化しつつあり、とくに小児医療においては、少子化や予防医学の進歩などによる患者の減少も含め、採算面の問題から小児科を廃止する病院もみられるなど、かなり厳しい状況となっています。
同様に、肢体不自由児施設をとりまく環境も極めて厳しくなってきており、全国の肢体不自由児施設における入所児数は、30年前頃までは増加の一途でしたが、昭和52年の7,129名をピークに、その後毎年ほぼ100名〜200名ずつ減少し、平成17年度には2,507名と激減しています。
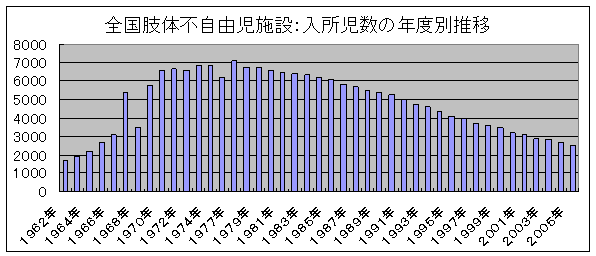
実際、入所児数の減少による経営上の問題から重症心身障害児・者の入所施設や障害児の通園施設への転換を余儀なくされた施設も少なからずみられ、昭和52年度には76施設ともっとも多かったのですが、その後徐々に入院児数の減少とともに施設数も減少を続け、平成18年度には62施設となっています。62施設のうち27施設が公立・公営、12施設が公立・民営、23施設が民立・民営であり、民営の施設が56%を占めており、現在そのほとんどが経営面から存亡の危機に立たされていると言っても過言ではありません。
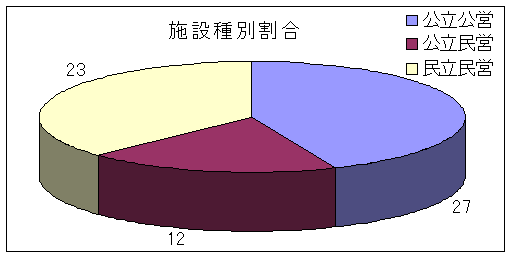
前述のように、全国の施設数は76施設から62施設と14施設の減少がみられていますが、そのうち11施設が「重症心身障害児入所施設」、2施設が病棟を閉鎖した「通園施設」へと施設種別を変更した運営方法の方向転換でした。しかし5年前、静岡県の民立・民営施設である浜松リハビリテーションセンターが入所児の減少などによる経営難から廃止となりました。これは、昭和17年に本邦初の肢体不自由児施設である整肢療護園(現在の心身障害児総合医療療育センター)が東京都板橋に開園して以来、約65年間にも及ぶ肢体不自由児施設の長い歴史上、初めての出来事であり、関係者に大きな衝撃を与えました。ま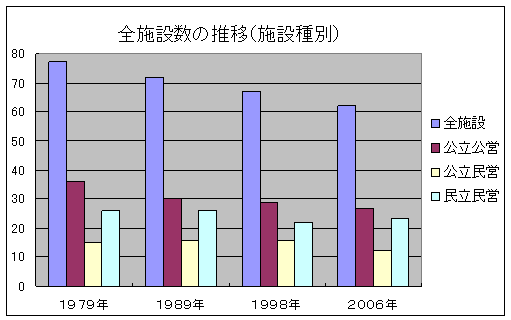 たこの数年、整形外科・リハビリテーション科関連の診療報酬が大幅に減額されたことから、整形外科、リハビリテーション科が大きな役割を担い、収入の大部分を占めている肢体不自由児施設の経営面にさらに深刻な陰をおとしています。 たこの数年、整形外科・リハビリテーション科関連の診療報酬が大幅に減額されたことから、整形外科、リハビリテーション科が大きな役割を担い、収入の大部分を占めている肢体不自由児施設の経営面にさらに深刻な陰をおとしています。
ところで、このような入所児数の減少は、ノーマライゼーション理念の浸透による普通学級はもちろん障害児学級の新設も含めた地域の学校での受け入れの改善や肢体不自由児養護学校(平成19年度から特別支援学校)の増設などが大きく影響していると考えられ、障害児をとりまく社会状況は徐々に改善傾向にあると思われます。一方で、肢体不自由児施設にとっては運営・経営上、非常に難しい問題が生じてきています。
|
全国の肢体不自由児施設における入所率は、平成16年度現在で平均約60%で、公立・民営施設がもっとも高く、次いで民立・民営、公立・公営の順となっています。当施設では、入所定数60名に対して入所率約70%と全国平均をやや上回っていましたが、今年度は60%程度となっており、全国的な傾向をみても、今後の入所児数の減少傾向が懸念されています。
また、全介助児など重度重複障害児の入所割合が増加傾向を示していますが、両親の離婚や虐待も含めた家庭環境に問題のある社会的入所児の占める割合の増加傾向がみられています。
入所期間に関しては、平成16年度の入院期間別割合では、5年間以上のいわゆる「長期入所児」の割合が30%以上を占めており、3年間以上も含めると約50%となっています。
入院期間別割合の推移からは、長期入所はもちろんですが、3ヶ月から6ヶ月程度の入所児割合も増加傾向を示しており、手術および術後のリハビリテーションを目的とした比較的短期間の入所児の増加もひとつの因子と考えられます。
肢体不自由児施設を業務内容の割合から、手術などを数多く行っている医療業務が比較的多い「医療型」、重度障害児数が多く福祉業務の占める割合が比較的高い「福祉型」、その中間の「中間型」の3種類に大まかに分ける場合があります。「医療型」の施設では、手術対象が多いことから入所期間は比較的短期の障害児が多く、「福祉型」の施設ではおそらく長期入所の占める割合が多くなっていると思われます。敢えて当てはめるとすれば、当施設はおそらく「中間型」に位置していると考えられます。
![]()