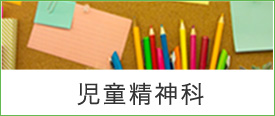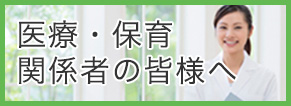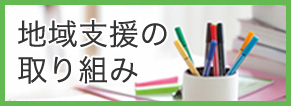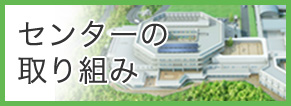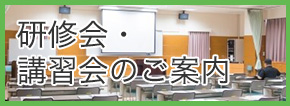令和7年度「ここ・から」研修会を開催しました
テーマ『災害時、子どもの育ちを支えるために何ができるか』令和7年7月29日(火)に「災害時、子どもの育ちを支えるために何ができるか」と題し、三重県総合文化センター文化会館中ホールにて平成7年度「ここ・から」研修会を開催しました。教育、行政、福祉、医療関係者など県内から268名の方にご参加いただきました。
午前は、「能登半島地震から学んだこと~医療的ケア児支援を中心に~」と題し、国立病院機構医王病院小児科(副院長)丸箸圭子氏にリモートにてご講演をいただきました。講演では、能登半島地震での支援のご経験から、院内に設置のいしかわ医療的ケア児支援センターこのこのが、関わりのある児について状況の把握や必要物資の把握、支援につなげる役割を担ったことをご紹介いただき、そのうえで、災害が起こる前から支援者とつながりを持っておくこと、避難計画とともに訓練や防災キャンプを通して実際に体験しておくことが大事とのお話がありました。

その後、「もしもに備える~災害時の肢体不自由児支援の実践と課題~」と題し、シンポジウムを行いました。まず、鈴鹿医療科学大学保健衛生学部リハビリテーション学科理学療法学専攻助教多田智美氏にJRAT(※)活動の一環として能登半島地震にて支援をされたご経験から日頃から顔の見える関係を築いておくこと、必要な支援や行動を予め考えておくことの重要性をお話しいただき、名張市なばりの未来創造部危機管理室稲垣和幸氏に、市において個別避難計画を作成されたご経験から、個別避難計画を立てること自体が連携の強化につながること、災害時には行政だけでなく地域社会全体の協力が不可欠であることなどをお話しいただきました。これに対し、三重県防災対策部地域防災推進課長長井健治氏から避難行動要支援者に対する個別支援計画の作成があまり進んでいないという課題が示されました。
※JRAT…一般社団法人日本災害リハビリテーション支援協会。

午後は、「災害時にも子どもの育ちを支える~その時、何が求められ、何ができるのか~」と題し、仙台市健康福祉局障害福祉部参事兼精神保健福祉総合センター所長林みづ穂氏からご講演をいただきました。講演では東日本大震災後、子どものこころのケアに携わったご経験から、被災後に子どもに現れる心身の変化、それに対する具体的な対応の仕方や留意しなければならないことなどをお話しいただきました。

講演後は、「災害時のこころのケアを考える」と題しシンポジウムを行いました。シンポジウムでは、三重県教育委員会学校防災アドバイザー・多気町防災ネットワークグループ大須賀由美子氏より学校での防災教育の様子をご紹介いただくとともに、学校は避難所としての機能も持つが、子どもの日常の場であり被災後早期の学校再開が必要であるとの共通認識を持つことが重要とのお話がありました。三重県自閉症協会会長勝又亜里砂氏からは災害時に備え、自閉症児の特性を多くの方に知っていただきたいこと、協会として災害時にできることについて発表がありました。また、子ども心身発達医療センター長中西大介から、大地震が起こった場合に、センターは医療機関としての機能維持が第一優先となり十分な地域支援は難しいだろうとのお話をいたしました。
これに対し、林みづ穂氏から、災害に備えそれぞれの機関が何をしていて、どんなことを期待しているのかを皆が知っておくことが大切で、この研修会で知ったことをぜひ広めてほしい。また、災害時には自身のケアも大事と心に留めてほしいとのご助言をいただきました。

参加者からは、端的でわかりやすかった、今後の参考にしていきたいなどのご意見をいただきました。アンケートの結果をもとに、よりよい研修を企画していきたいと思いますので今後とも、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
過去の開催結果
令和6年度「ここ・から」研修会 開催概要(令和6年7月25日)
令和5年度「ここ・から」研修会 開催概要(令和5年8月1日)
第4回小児整形・児童精神合同研修会 開催概要(令和4年7月29日)
第3回小児整形・児童精神合同研修会 開催概要(令和3年7月27日)
第2回小児整形・児童精神合同研修会 開催概要(令和元年7月30日)
第1回小児整形・児童精神合同研修会 開催概要(平成30年7月27日)