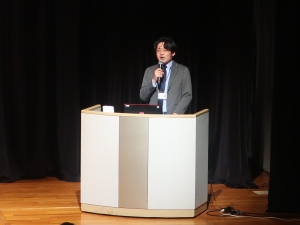今回の講座は三重県生涯学習センターとの共催講座で、男女共同参画センター「フレンテみえ」の多目的ホールを会場に、「三重の古墳時代の土器生産」と題した講座を行い、会場に98名、オンライン視聴で86名の方が参加されました。
講座では、土師器と須恵器の違いにはじまり、土師器生産が中心であった古墳時代の三重県に、どのような形で須恵器生産の技術が伝来したのか、六大A遺跡(津市)の出土遺物をもとに説明しました。その後、ヲノ坪窯跡、久居古窯跡、内多窯跡(いずれも津市)、明気窯跡群(多気町)の出土遺物をもとに、須恵器生産技術の伝播や、大和王権と地域の首長層との関係性などについても話がありました。さらに、葬送用具としての須恵器の変遷や、伊勢地域最大の須恵器生産地であった徳居古窯跡群(津市、鈴鹿市)、伊賀地域での須恵器生産、同時期での土師器生産についても説明がありました。
会場には、講座で紹介した遺跡の出土遺物を展示しました。講座の開始前や休憩時間に参加者の皆さんは興味深くご覧になり、一つ一つについて職員や講師に質問されていました。
三重県生涯学習センターとの共催講座ということもあり、10代から80代の幅広い世代の方にご参加いただき、講座を楽しんでいただきました。
今回は土器生産というテーマを絞った講座となりましたが、事後アンケートには、「どこから来た工人かの推論は、楽しいものであった。」「三重の須恵器生産について、ていねいに解説していただき大変勉強になりました。これをきっかけに自分でも学んでいきたいと思います」「内容が濃くすごくわかりやすかったですし、面白かったです」などの記述があり、楽しんでいただけた方が多かったようです。(活用支援課)