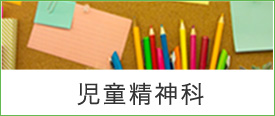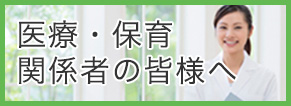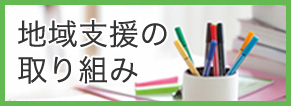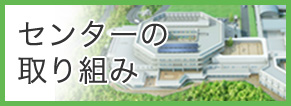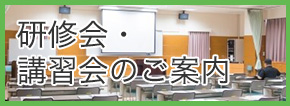リハビリテーション科
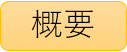
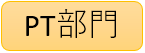
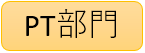
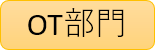
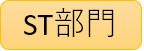
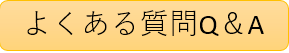
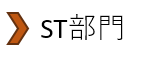
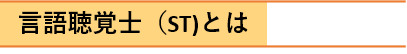 子どもを対象とした言語聴覚療法では主に、ことばやコミュニケーションの力を育てるためのかかわりや、保護者への助言を行います。 また、摂食機能療法では、食べる機能を獲得する過程で経験する様々な課題に対して、評価・相談・支援を行います。 |
 |
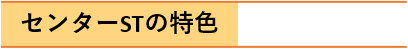 <言語> ことばの遅れやコミュニケーションに課題があるお子様に対し、遊びや検査場面を通じて評価し、お子様の発達段階に合わせた支援を実施します。時にはままごとなどの遊びの場面で、時には絵カードやプリントなどを使用した学習場面など、生活場面に応じたサポートを行いながら、家庭や日常生活でも継続して実施できるようにアセスメントします。 <摂食> 食事に関する困りごとに対して、食事場面の観察などから摂食嚥下機能の発達段階を評価します。食形態や食事姿勢、介助方法などについて、保護者と相談しながらお子様の食環境を整えられるようサポートします。 |
 |
<言語> 〇LD(学習障害)評価 児童精神科医や心理部門と連携し、評価・関係機関への助言(フィードバック)を行う、LD評価システムを実施しています。 〇吃音 未就学児へのリッカムプログラムの他、思春期の吃音に対する支援など、ライフステージに合わせたサポートを実施しています。 〇AAC(拡大・代替コミュニケーション) 音声言語の表出が難しいお子様に対して、PECS🄬などの絵カードコミュニケーションや、視線入力機器を使用したコミュニケーション評価・支援・活用を実施しています。 |
| <摂食> 〇嚥下造影検査(VF)等による検査評価 他院小児科医等と連携した検査評価により、姿勢や食形態について検討しています。 〇嚥下調整食に関する食事支援 摂食嚥下機能や発達段階に合った食事が家庭で食べられるように、管理栄養士、調理師と連携しながら栄養面や調理についてサポートを実施しています(調理支援等)。 〇乳幼児期からの摂食リハ実施 離乳食の進め方やかかわり方など、保護者の困り事が出やすい0歳児の時期から、評価・相談・支援を実施しています。 〇偏食相談・支援 主に児童精神科主治医とともに、偏食相談に対し、摂食嚥下機能評価だけでなく、食形態や味覚、さらに食事場面での工夫などをサポートしています。 |
 |
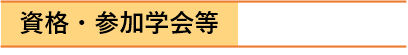
<資格>
〇福祉用具専門相談員
〇認定言語聴覚士(言語発達障害領域)
〇認定言語聴覚士(吃音・小児構音障害領域)
〇認定言語聴覚士(摂食嚥下障害領域)
<参加学会・研修会等>
●日本言語聴覚士協会
●日本LD学会
●日本摂食嚥下リハビリテーション協会
●日本吃音流暢性協会
●子どもの発達支援を考えるSTの会
●全国肢体不自由児療育研究大会(発表
●マカトン法ワークショップ
●PECS レベル1,レベル2
●リッカムプログラム臨床研修会
●RASS吃音研究会 基礎編、実践編
●SST初級研修
●臨床実習指導者講習(ST協会)
●近代ボバース概念(CBC)小児領域8週間基礎講習会