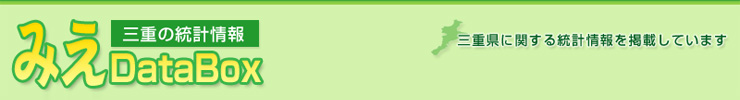2 利用上の注意
1 数値について
(1) 今回公表の数値は、概数値であり確定値ではない。
なお、確定値は農林水産省が平成14年3月までに刊行物として公表する。
(2) 数値は、ラウンドしてあるため、総数とその内訳を合計したものとが一致しない場合がある。
また、説明文中の各表の増減数、増減率、構成比や統計表中の構成比等はラウンド前の原数値より算出しているため、表上の数値で算出したものと若干の差が生じる場合がある。
(3) 定義の変更
林業事業体の定義
1990年(平成2年)以前は、林業事業体の定義が「旧定義」のため数値の取扱いには留意されたい。
(旧定義)
保有山林面積が10a以上(1990年世界農林業センサスまで)
(新定義)
保有山林面積が1ha以上(2000年世界農林業センサスから変更)
(4) 面積の取扱いについて
農林業センサスは属人調査(属地ではない)であるため、調査対象が他の市区町村又は県外に農地や山林を保有している場合、その経営耕地面積や保有山林面積はその農家や林家のある市町村の面積に計上されるので留意されたい。(市町村又は県を越えて面積のやり取りがある)
(5) 表中に使用した符号は、次のとおりである。
「-」 は事実のないもの
「…」 は調査を欠くもの
「0」 は単位に満たないもの
「△」 は減少したもの
「×」 は数値を秘匿したもの
(参考)
調査客体の秘密保護の観点から市町村を表章地域範囲とする場合、2客体以下については、総客体数以外の調査項目は公表しないこととする。(プライバシーの保護のため「x」と表す)。また、農業集落を表章地域とする場合は、総客体数以外が4客体以下については、総客体数以外の調査項目は公表しないこととする。
2 地域区分について
| 地域 | 市郡名 |
|---|---|
| 北勢地域 | 四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、桑名郡、員弁郡、三重郡、鈴鹿郡 |
| 中勢地域 | 津市、松阪市、久居市、安芸郡、一志郡、飯南郡、多気郡 |
| 南勢地域 | 伊勢市、鳥羽市、度会郡、志摩郡 |
| 伊賀地域 | 上野市、名張市、阿山郡、名賀郡 |
| 東紀州地域 | 尾鷲市、熊野市、北牟婁郡、南牟婁郡 |
3 定義・約束事項
(1) 農家調査
|
農家 |
平成12年2月1日現在の経営耕地面積が10a以上の農業を営む世帯。または、経営耕地面が10a未満であっても調査期日前1年間の農産物販売金額が15万円以上あった世帯(例外規定農家)をいう。 |
|---|---|
|
販売農家 |
経営耕地面積が30a以上または農産物販売金額が50万円以上の農家をいう。 |
|
自給的農家 |
経営耕地面積が30a未満かつ農産物販売金額が50万円未満の農家をいう。 |
 |
|
|
経営耕地面積 |
農家が経営する耕地(田、畑、樹園地の計)をいう。 自己所有地-耕作放棄地-貸付耕地+借入耕地 |
|
田 |
耕地のうち、水をたたえるためのけい畔のある土地のことをいう。 |
|
畑 |
耕地のうち、田と樹園地を除いた耕地をいう。 |
|
樹園地 |
木本性周年作物を周期的または連続的に栽培している土地で、同一種類が1a以上まとまっているもので肥培管理しているものをいう。 |
|
耕作放棄地 |
以前耕地であったもので、過去1年以上作物を栽培せず、しかも、今後数年の間に再び耕作する意志のない土地をいう。(多少手を加えれば耕地になる土地) |
|
貸付耕地 |
他人に貸し付けている自己所有耕地をいう。 |
|
借入耕地 |
他人から耕作を目的に借り入れている耕地をいう。 |
|
主業農家 |
農業所得が主(農家所得のうち50%以上が農業所得)で、65歳未満の農業従事60日以上の者がいる農家をいう。 |
|
準主業農家 |
農業所得が従(農家所得のうち50%未満が農業所得)で、65歳未満の農業従事60日以上の者がいる農家をいう。 |
|
副業的農家 |
65歳未満の農業従事60日以上の者がいない農家をいう。 |
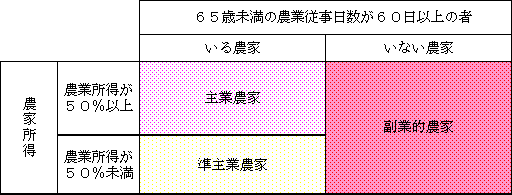 |
|
|
専業農家 |
世帯員の中に兼業従事者が1人もいない農家をいう。 |
|
兼業農家 |
世帯員の中に兼業従事者が1人以上いる農家をいう。 |
|
第1種兼業農家 |
農業所得が主(50%以上)である兼業農家をいう。 |
|
第2種兼業農家 |
農業所得が従(50%未満)である兼業農家をいう。 |
|
単一経営農家 |
農産物販売金額のうち、第1位の部門の販売金額が8割以上の農家をいう。 |
|
準単一複合経営農家 |
農産物販売金額のうち、第1位の部門の販売金額が6割以上8割未満の農家をいう。 |
|
複合経営農家 |
農産物販売金額のうち、第1位の部門の販売金額が6割未満の農家をいう。 |
|
農業投下労働規模別分類 |
農業経営に投下された総労働量を標準化した値で比較するため、2000年世界農林業センサスから採用した。年間農業労働時間1,800時間(1日8時間換算で225日/人)を1単位の農業労働単位とし、農業経営に投下された総労働日数を225日で除した値により分類を行うものである。 |
|
家族経営構成別分類 |
家族経営の労働力構成、経営への家族の参画状況等を明らかにするため、家族経営構成員の世帯構成による分類として、2000年世界農林業センサスから採用した。 |
|
一世代家族経営 |
家族経営構成員が、経営主1人又は経営主夫婦等一世代で構成されるものをいう。なお、経営主をその兄弟による経営は一世代とした。 |
|
二世代家族経営 |
家族経営構成員が、経営主と子又は経営主と親又は経営主と孫等二世代で構成されるものをいう。 |
|
三世代家族経営 |
経営主、子及び孫等三世代で構成されるものをいう。なお、経営主のおじ、おば、いとこ等を含むものも三世代等とした。 |
|
農業従事者 |
満15歳以上の世帯員のうち、調査期日前1年間に農業に1日以上従事した者をいう。 |
|
農業専従者 |
満15歳以上の世帯員のうち、調査期日前1年間に農業に150日以上従事した者をいう。 |
|
農業就業人口 |
農業に主として従事した世帯員のことをいい、調査期日前1年間に「農業のみに従事した世帯員」及び「農業と兼業の双方に従事したが、農業の従事日数の方が多い世帯員」のことをいう。 |
|
基幹的農業従事者 |
農業に主として従事した世帯員(農業就業人口)のうち、調査期日前1年間のふだんの主な状態が「仕事に従事していた者」のことをいう。 |
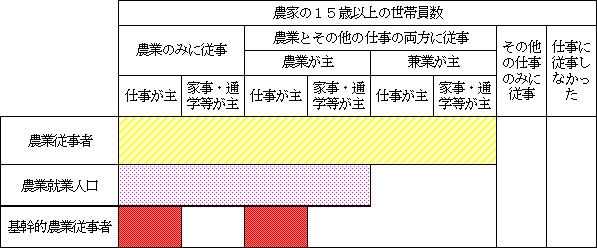 |
|
(2) 農家以外の農業事業体調査
|
農家以外の農業事業体 |
前記(1)で規定する農家以外で農業を営む事業体であって、経営耕地面積が10a以上あるもの。または、経営耕地面積がそれ未満であっても調査期日前1年間の農産物販売金額が15万円以上あるものをいう。 |
|---|---|
|
経営目的 |
|
|
1 販売 |
農産物の販売により農業収入を得ることを直接の目的とした事業体をいう。 |
|
2 牧草地経営体 |
牛馬の預託事業を営むことを目的とした事業体及び共同して牧草を栽培し、共同で採草、放牧に利用することを目的とした事業体をいう。 |
|
3 その他 |
試験研究、学校、厚生、食料自給等を目的とした事業体をいう。 |
|
協業経営体 |
2戸以上の世帯が農業経営に関し、栽培、飼育、販売、収支決算等一切の過程を共同して行い、収益を分配しているものをいう。 |
|
株式会社 |
商法(明治32年法律第132号)に基づく株式会社の組織形態をとっているものをいう。 |
|
有限会社 |
有限会社法(明治13年法律第74号)に基づく会社法人の組織形態をとっているものをいう。 |
|
合名・合資会社 |
商法に基づく合名会社と合資会社の組織形態をとっているものをいう。 |
|
農協・その他の農業団体 |
農業共同組合法に基づく農業協同組合、農協の連合組織、農業災害補償法に基づく農業共済組合や農業関係の団体をいう。 |
(3) 林家調査
|
林家 |
平成12年2月1日現在の保有山林面積が1ha以上の世帯をいう。 今回、定義の変更を行っており、1990年センサスまでは、保有山林面積が、10a以上の世帯としていた。 |
|---|---|
|
農家林家 |
林家のうち、農家である世帯をいう。 |
|
非農家林家 |
林家のうち、非農家である世帯をいう。 |
|
林家以外の林業事業体 |
平成12年2月1日現在(沖縄県にあっては、平成11年12月1日現在)で、保有山林の各筆の面積のいずれかが1ha以上ある会社、社寺、共同、各種団体・組合、財産区、慣行共有、市区町村、地方公共団体の組合、都道府県、国及び特殊法人をいう。 今回、定義の変更を行っており、1990年センサスまでは、保有山林面積10a以上の事業体としていた。 なお、慣行共有及び財産区とは以下のものをいう。 慣行共有とは、次の3つの条件のうちいずれかに該当するものをいう。 1 山林からの収入や林産物を「ムラ」の費用や公共の事業に使うことがあること。 2 その山林は、昔からのしきたりで持っている、または利用している、あるいは利用させていること。 3 山林の特権者になる資格に、特定の「ムラ」に住んでいるものに限るという制限があること。 これは、一般的に「ムラ」有林と呼ばれているもの、またはそれに近いものであって、実質的な使用収益が多かれ少なかれ、慣行として共同体的制約を受けると認め・轤黷驍烽フという。 財産区とは、市区町村の一部の山林を財産として持っているものをいう。 |
|
山林 |
用材、薪炭材、竹材その他の林産物を集団的に生育させるために用いる土地をいい、台帳地目にかかわらず現況によった。したがって、樹木が生えていても樹園地及び庭園は山林から除いた。 |
|
保有山林 |
世帯が単独で経営できる山林のことであり、所有山林のうち他に貸し付けている山林などを除いたものに他から借りている山林などを加えたものをいう。 |
|
林産物の販売 |
保有山林から生産された林産物(用材、ほだ木用原木、林野特産物をいい、買山からの素材、栽培きのこ類、林業用苗木などは除く。)について過去1年間に販売(自家消費に向けたものを含む。)したものをいう。 |
|
林家の主業 |
世帯の生計の主なよりどころになっている仕事をいう。二つ以上の異なった仕事がある場合は、所得の最も多いものを主業とした。 |
|
林業従事世帯員 |
過去1年間に自分の家の林業の作業やよそに雇われて林業の作業に従事した世帯員をいう。 |
|
植林 |
山林とするために、伐採跡地や山林でなかった土地へ苗木を植えたり、種子をまいたり、さし木したりする作業をいうが、植林の地ごしらえ、苗木運搬など一連の作業をいう。 |
|
下刈りなど |
材木の健全な育成のために行う下刈り作業と除伐、つる刈り、枝打ち、雪起こしなど間伐以外の保育作業をいう。 |
|
間伐 |
除伐後に行う作業で森林を健全に成長させるため、劣性木、不要木を抜き切りすることをいう。 |
|
主伐 |
一定の林齢に生育した材木を、用材等で販売するために行う除伐・間伐以外の伐採をいう。 なお、立木のまま販売したものは含まない。 |