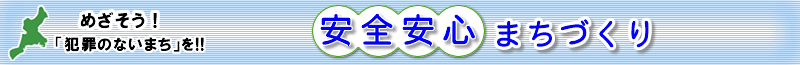|
【会議の内容】
1.生活部長あいさつ
2.委員紹介
3.議事内容
(1)会長等選出
(2)平成18年度安全安心まちづくり事業に関する県の取組について【生活部】
(3)三重県の犯罪情勢と声かけ事案の発生状況について【警察本部】
(4)平成18年度の子どもの安全にかかる活動状況について【教育委員会】
4.意見交換会 「安全で安心なまちづくりのため取り組まれている防犯対策」について
【意見交換会における主な意見 (要旨のみ)】
1.現在の取組
- 登下校中の児童が何かあった時に駆け込める家となるように、自宅を子どもが気軽に立ち寄れるような試みを行っている。
- 自主防犯活動団体、学校、スクールガードリーダー等の関係機関がスムーズな連携をはかれるような取組を行っている。
- PTAと学校側が意思疎通をはかり学校が望んでいる防犯グッズを購入し貸与する等連携をはかっている。
- 企業にも参加してもらい、通学路の安全を確保する組織を設立し活動を行っている。
- 所属している団体で、通学路を見守る等の活動を行っている。
2.子どもを守る家の名称統一について
- 子どもの立場からすれば、子どもを守る家の名称やマークやジャンパーの色が統一されていないと混乱してしまうので県下で統一して欲しい。
- 行動範囲の狭い子どもにとっては、今まで慣れ親しんだ旗やマークは別々でもかまわない。大切なのは、子どもを守る家の看板を掲げることだけでなく子どもが気軽に利用できるということが重要である。
3.子どもへの教育
- 犯罪に遭わないための防犯教育も重要であるが、悪い人間に育てないための教育も重要である。
- そのためには、命の大切さを教える道徳教育やルールを守ること・正義・社会性の大切さを教えることも重要で、さまざまな面で防犯教育を進めていく必要がある。
4.関係団体・組織等との連携
- 自主防犯活動団体、スクールガードリーダー、PTA、健全育成会、学校、その他関係団体との結びつきが希薄である場合が多いが、意思疎通を図り連携することが良好な関係を構築するうえで重要である。
- ひいてはこれが、地域安全に結びついている。
5.その他
- 社会変化を認識できるようなさまざまな情報提供を行うことが、防犯を自分自身の問題としてとらえることができることに役立つ。
- まちの環境、美化、道路環境などさまざまな面にも目を向けるということが防犯には重要である。
議事録(PDF:66KB)
|