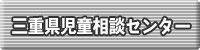児童扶養手当について
目的
父母の離婚・父または母の死亡、その他の事情により、父または母と生計を同じくしていない児童や、父または母が重度の障がいの状態にある児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について手当を支給し、児童の福祉の増進を図るための制度です。
支給要件
【 対象となる児童 】
・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が政令で定める程度の障がいの状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童
・父母とも不明である児童
上記のいずれかの条件に当てはまる児童を監護している母や、監護し生計を同じくしている父、あるいは父または母に代わってその児童を養育している人(養育者)が、児童扶養手当を受けることができます。
なお、この制度における「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童をいい、政令で定める程度の障がいの状態にある場合は、20歳未満の児童をいいます。
ただし、次のような場合は、手当を受けることができません。
【 受給者が母または養育者の場合 】
・受給者または児童が、日本国内に住所を有しないとき
・児童が、児童福祉施設等に入所しているとき、または里親に委託されているとき
・児童が、父と生計を同じくしているとき(ただし父が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く)
・児童が、母の配偶者(事実上の婚姻関係も含む)に養育されているとき
【 受給者が父の場合 】
・受給者または児童が、日本国内に住所を有しないとき
・児童が、児童福祉施設等に入所しているとき、または里親に委託されているとき
・児童が、母と生計を同じくしているとき(ただし母が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く)
・児童が、父の配偶者(事実上の婚姻関係も含む)に養育されているとき
手当の額(令和7年4月以降)
| 対象児童数 | 全部支給の方 | 一部支給の方 |
|---|---|---|
| 第1子 | 月額 46,690円 | 月額 46,680円 ~ 11,010円 |
| 第2子以降 | 月額 11,030円 | 月額 11,020円 ~ 5,520円 |
| ※一部支給の額は所得額に応じて決定されます。 | ||
一部支給の手当額の計算方法について(令和7年4月1日から)
A:受給者の所得額
B:全部支給の所得制限限度額
手当月額 第1子 = 46,680円 -{ (A-B) × 0.0256619 }
手当月額 第2子以降 = 11,020円 -{ (A-B) × 0.0039568 }
※{ }の中は10円未満四捨五入
※Bの額は扶養親族等の数によって変わります。所得制限限度額表をご覧ください。
支給の制限
手当の額は、受給者または配偶者及び扶養義務者※1の前年の所得※2によって「全部支給」「一部支給」「支給停止(支給なし)」が決定されます。
毎年8月に現況届をご提出いただき、児童の監護状況や、前年の所得等を確認したうえで、手当額が決定されます。
(※1)扶養義務者とは、請求者と同居している父母兄弟姉妹などのことです。
(※2)1月から9月の間に請求書を出す場合は、前々年の所得です。
所得制限限度額表(令和6年11月から現行の金額)
| 扶養親族等の数 | 受給者(父・母または養育者) | 扶養義務者/ 配偶者/孤児等の養育者 |
|
|---|---|---|---|
| 全部支給 | 一部支給 | ||
| 0人 | 690,000円未満 | 2,080,000円未満 | 2,360,000円未満 |
| 1人 | 1,070,000円未満 | 2,460,000円未満 | 2,740,000円未満 |
| 2人 | 1,450,000円未満 | 2,840,000円未満 | 3,120,000円未満 |
| 3人 | 1,830,000円未満 | 3,220,000円未満 | 3,500,000円未満 |
| 4人以上 | 1人につき 380,000円ずつ加算 |
1人につき 380,000円ずつ加算 |
1人につき 380,000円ずつ加算 |
| 加算額 | ・同一生計配偶者(70歳以上の者に限る) または老人扶養親族 →1人につき100,000円加算 ・特定扶養親族または16歳以上19歳未満の 控除対象扶養親族 →1人につき150,000円加算 |
・老人扶養親族 (扶養親族等のすべてが 老人扶養親族である 場合は1人を除き) →1人につき60,000円加算 |
|
【受給者の場合】
1 扶養親族等の数に対応する全部支給・一部支給の所得制限限度額を確認します。
2 所得が、
全部支給の所得制限限度額未満の場合は全部支給、
一部支給の所得制限限度額未満の場合は一部支給、
一部支給の所得制限限度額以上の場合は支給停止になります。
【扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者の場合】
1 扶養親族等の数に対応する所得制限限度額を確認します。
2 所得が所得制限限度額以上の場合は支給停止になります。
※受給者の所得が所得制限限度額未満の場合でも、扶養義務者または配偶者の所得が所得制限限度額以上の場合は支給停止となります。
所得額(市町の課税台帳による)の計算方法について
所得額 = 年間収入金額 + 養育費※1 - 必要経費 (給与所得控除額等)
- 8万円 (社会保険料相当額) - 10万円※2 - 諸控除
(※1) 養育費は、受給者が父または母の場合に、児童の母または父から児童の養育に必要な費用として受け取った金品等のことをいいます。受給者または児童が、前年(または前々年)に受け取った金品等の8割が養育費として所得に算入されます。
(※2) 10万円の控除は、給与所得、または公的年金等に係る所得がある場合に限ります。(事業所得のみの場合は、控除されません。)
| 諸控除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 障害者控除 | 27万円 | 雑損控除 | 当該控除額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特別障害者控除 | 40万円 | 医療費控除 | 当該控除額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤労学生控除 | 27万円 | 配偶者特別控除 | 当該控除額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寡婦控除※ | 27万円 | 小規模企業共済等 掛金控除 |
当該控除額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひとり親控除※ | 35万円 | 肉用牛の売却による 事業所得 |
当該控除額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※児童の母または父の場合、寡婦控除・ひとり親控除は諸控除の対象に含まれません。
手当を受けている方へ
現況届について
すべての受給者は、毎年8月1日から8月31日までの間に、現況届をご提出いただく必要があります(事前に通知いたします)。
現況届を提出されませんと、11月分以降の手当が受けられません。なお、2年間届出をしないと、時効により受給資格が消滅します。
一部支給停止措置について
手当を受給して5年、または手当の支給要件に該当して7年を経過したとき(3歳未満の児童を育てている場合は、3歳になってから5年を経過したとき)は、手当の2分の1が支給停止されます。
ただし、次の項目に該当する方は、期日までに児童扶養手当担当窓口に所要の書類をご提出いただければ、手当の2分の1が支給停止されることがなくなります。
- 就業している場合
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている場合
- 身体上または精神上の障がいがある場合
- 負傷または疾病等により就業することが困難である場合
- 児童または親族が負傷、疾病、障がい、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である場合
公的年金等を受給している方について
公的年金等を受給している方は、児童扶養手当担当窓口への届出が必要です。
公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などです。
・受給者が公的年金等を受給しているとき
・児童が公的年金等を受給しているとき
・父または母が受けている公的年金について、児童が加算の対象となっているとき
などの場合に、届出が必要です。
年金の請求をすれば支給されるものの、請求しないでまだ受けていない場合も対象となります。
ご不明な点がある場合は、一度児童扶養手当担当窓口にてご相談ください。
受給者または児童が公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受けることができるときは、児童扶養手当の全部または一部が支給停止になる場合があります。
公的年金等を受給できる場合は、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回るときは、その差額分の児童扶養手当を受給できます。
また、令和3年3月分からは児童扶養手当法の一部が改正され、児童扶養手当の額と障害基礎年金等の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できるよう見直されました。
公的年金等が過去にさかのぼって給付される場合や、公的年金を受給していることの届出が遅れた場合は、過去に受給した児童扶養手当の返還が必要になる場合がありますので、ご注意ください。
支給開始日
手当は請求日の属する月の翌月分から支給開始となります。
その他
(特別)児童扶養手当制度につき記載されているしおりを毎年作成しております。入手されたい場合は、お近くの市役所または町役場の児童扶養手当担当課にございますので、ご来訪ください。
申請窓口
| 居住市町 | 担当課 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 津市 | こども政策課 | 059-229-3155 |
| 四日市市 | こども手当・医療給付課 | 059-354-8083 |
| 伊勢市 | 子育て応援課 | 0596-21-5713 |
| 松阪市 | こども未来課 | 0598-53-4081 |
| 桑名市 | 子ども未来課 | 0594-24-1491 |
| 鈴鹿市 | こども政策課 | 059-382-7661 |
| 名張市 | 子ども家庭室 | 0595-63-7594 |
| 尾鷲市 | 福祉保健課 | 0597-23-8202 |
| 亀山市 | 子ども政策課 | 0595-84-3315 |
| 鳥羽市 | 健康福祉課 | 0599-25-1184 |
| 熊野市 | 福祉事務所児童福祉係 | 0597-89-4111 |
| いなべ市 | こども政策課 | 0594-86-7821 |
| 志摩市 | こども家庭課 | 0599-44-0282 |
| 伊賀市 | こども政策課 | 0595-22-9677 |
| 木曽岬町 | 子ども・健康課 | 0567-68-6119 |
| 東員町 | 子ども家庭課 | 0594-86-2872 |
| 菰野町 | 子ども家庭課 | 059-391-1227 |
| 朝日町 | 子育て健康課 | 059-377-5652 |
| 川越町 | 子ども家庭課 | 059-366-7130 |
| 多気町 | 健康福祉課 | 0598-38-1114 |
| 明和町 | こども課 | 0596-52-7123 |
| 大台町 | 福祉課 | 0598-82-3783 |
| 玉城町 | 保健福祉課 | 0596-58-8203 |
| 度会町 | 保健こども課 | 0596-62-2413 |
| 大紀町 | 住民課 | 0598-86-2217 |
| 南伊勢町 | 子育て・福祉課 | 0599-66-1114 |
| 紀北町 | 福祉保健課 | 0597-46-3122 |
| 御浜町 | 健康福祉課 | 05979-3-0508 |
| 紀宝町 | 福祉課 | 0735-33-0339 |